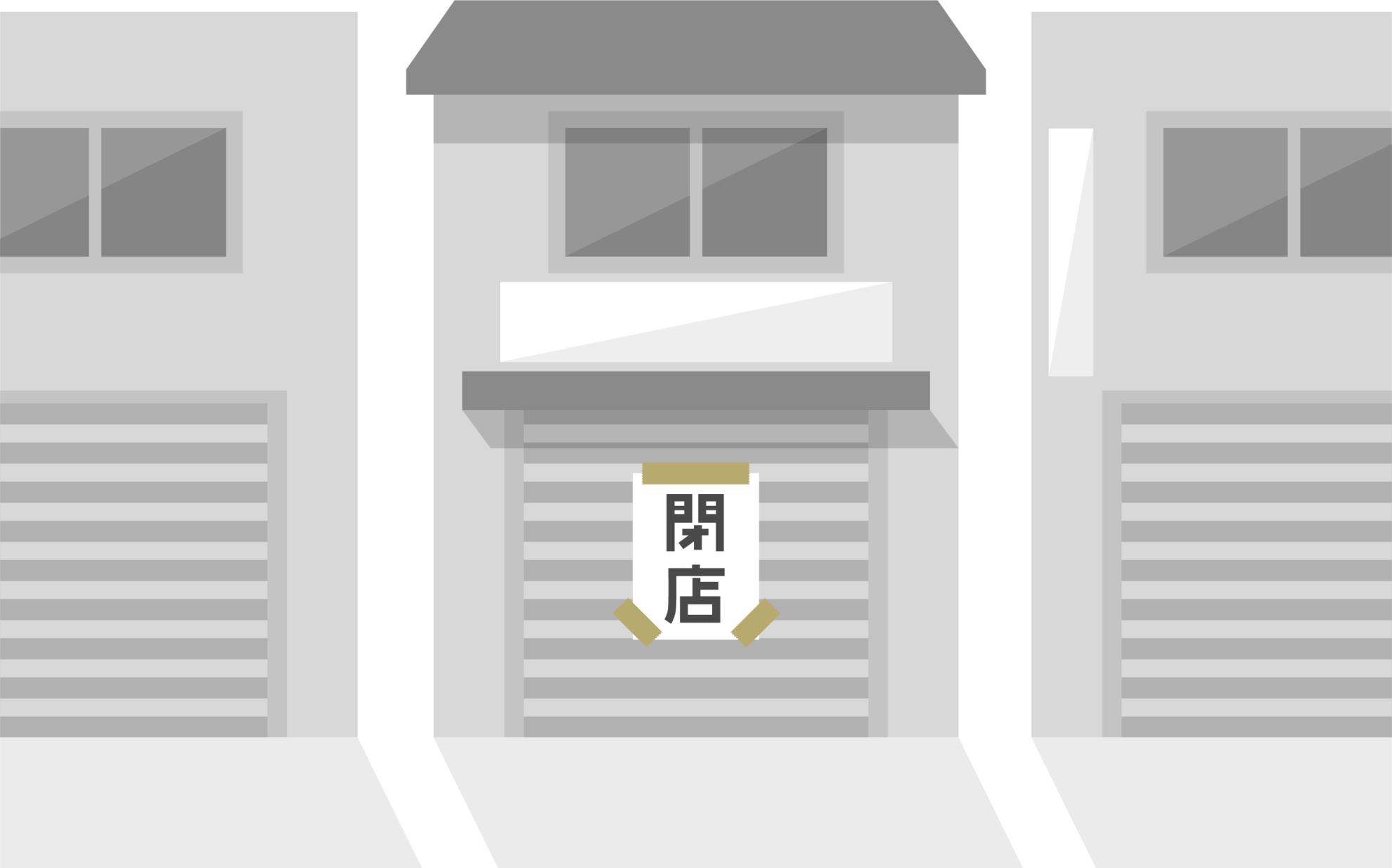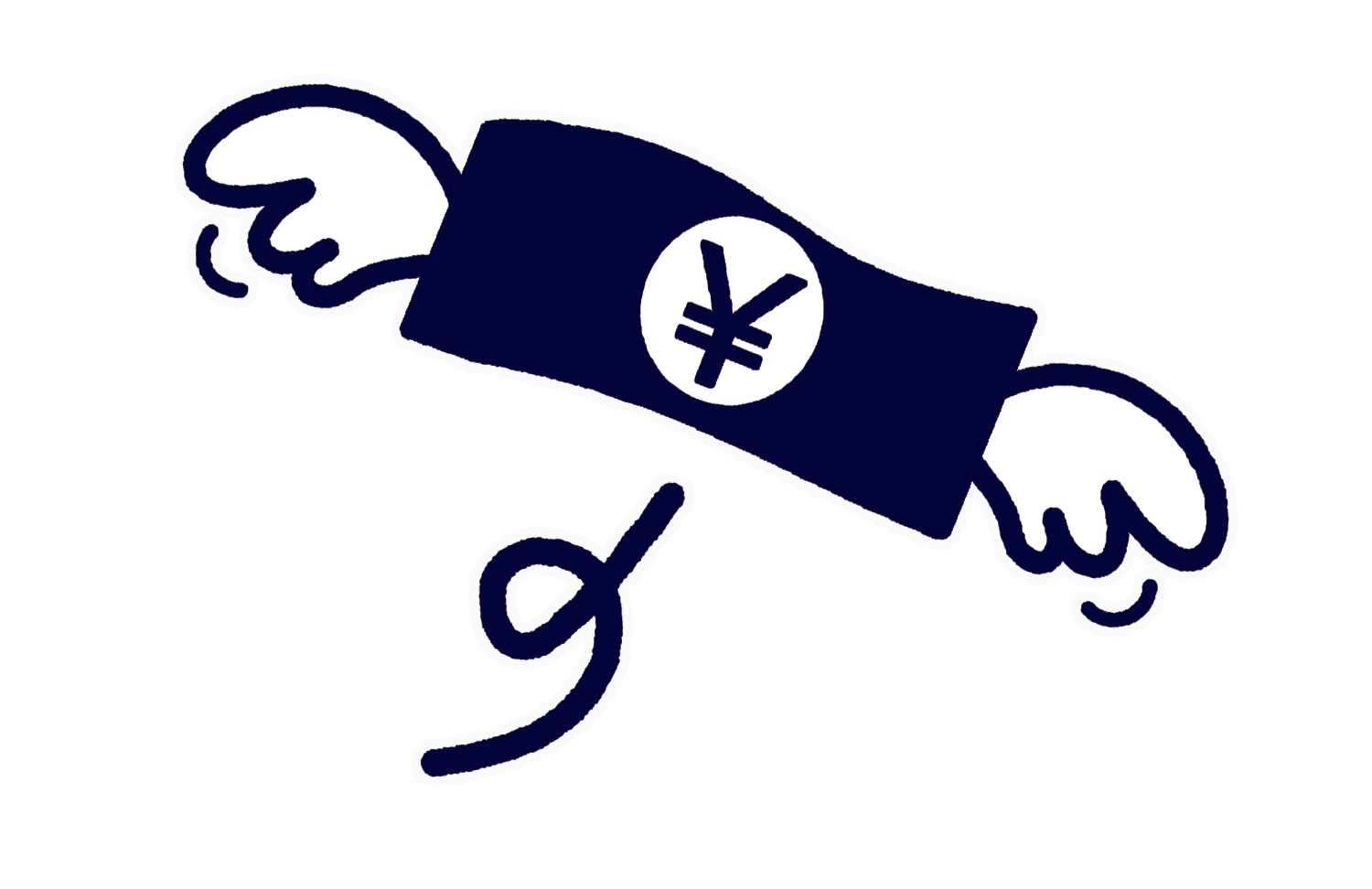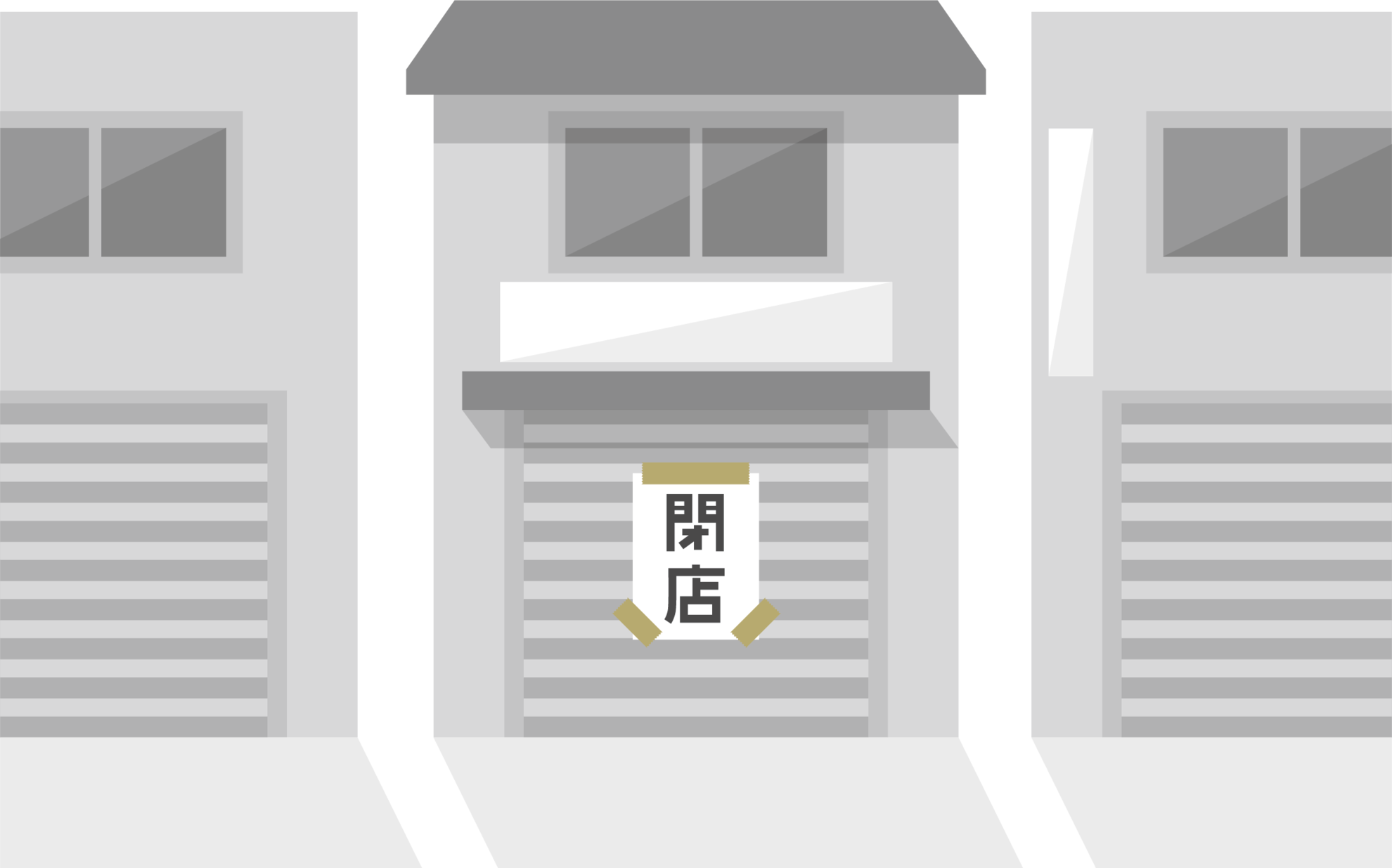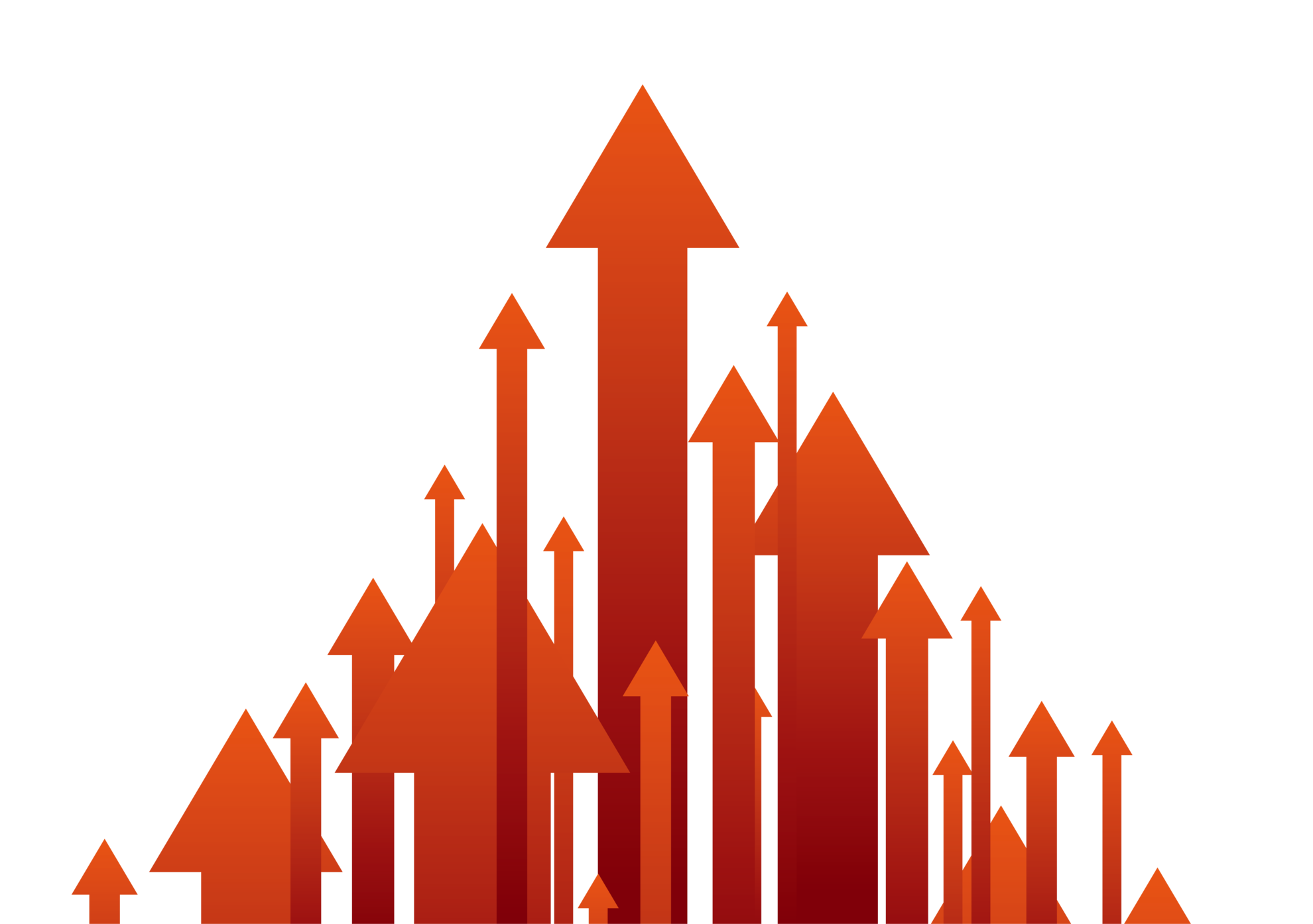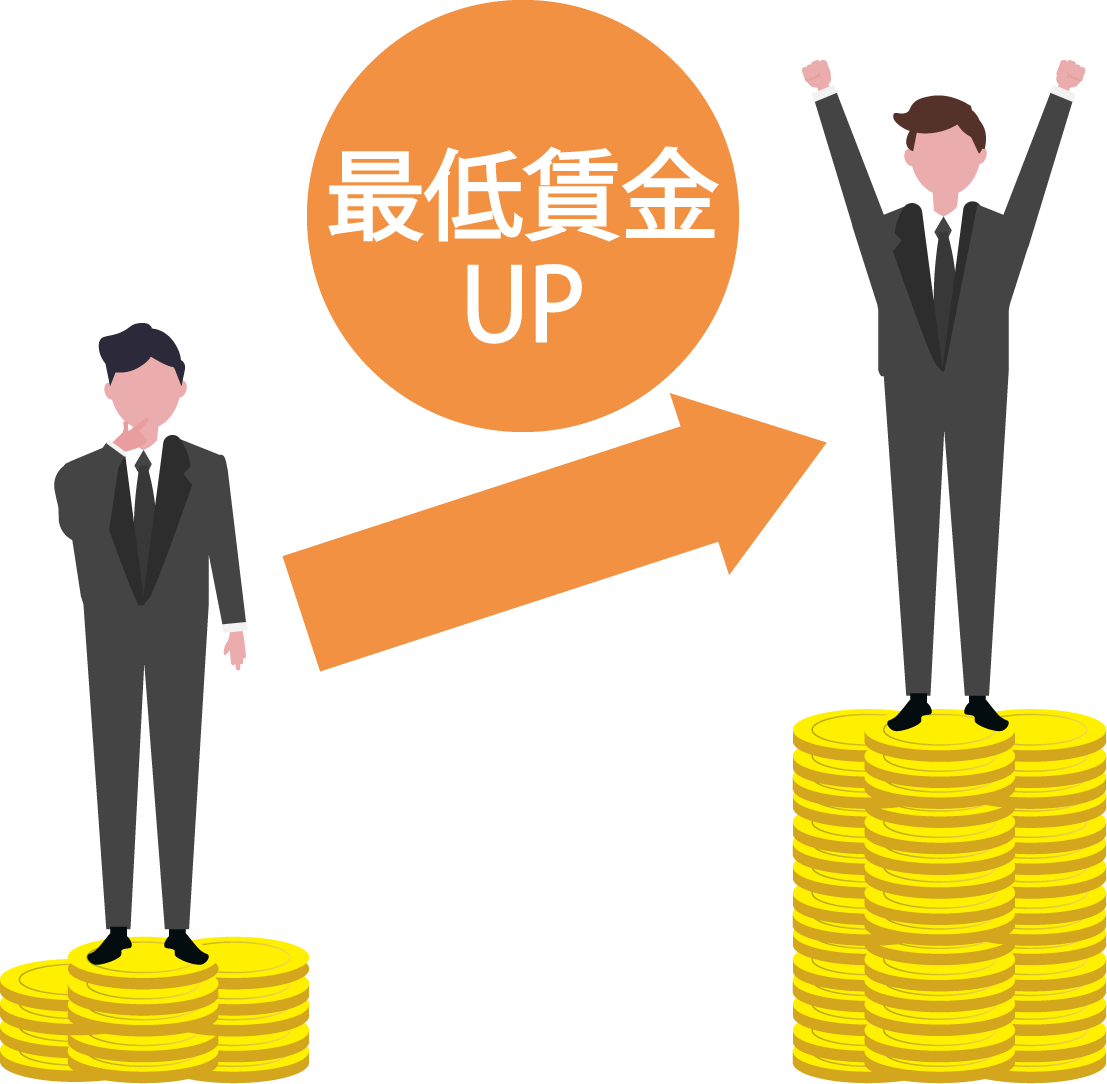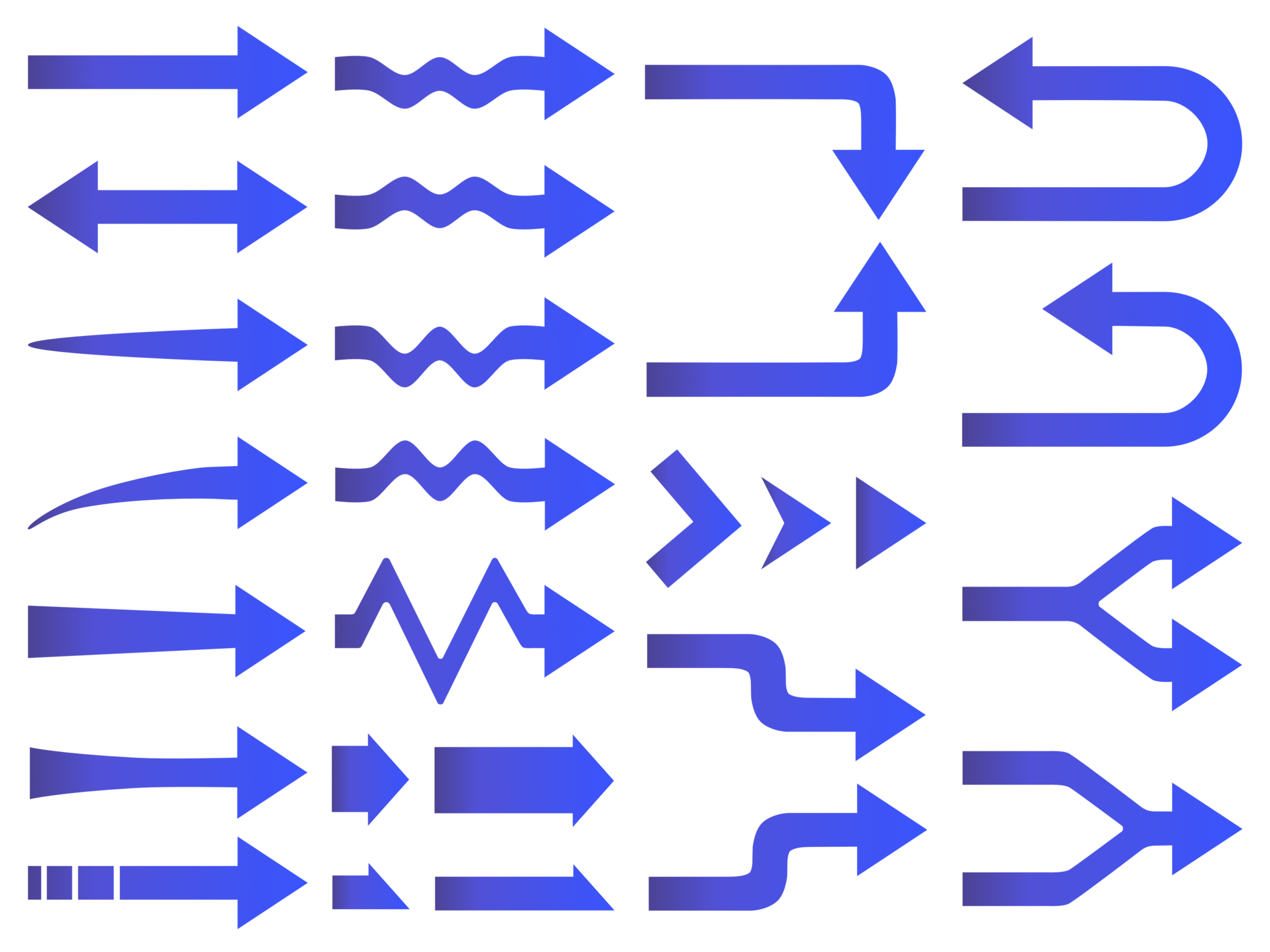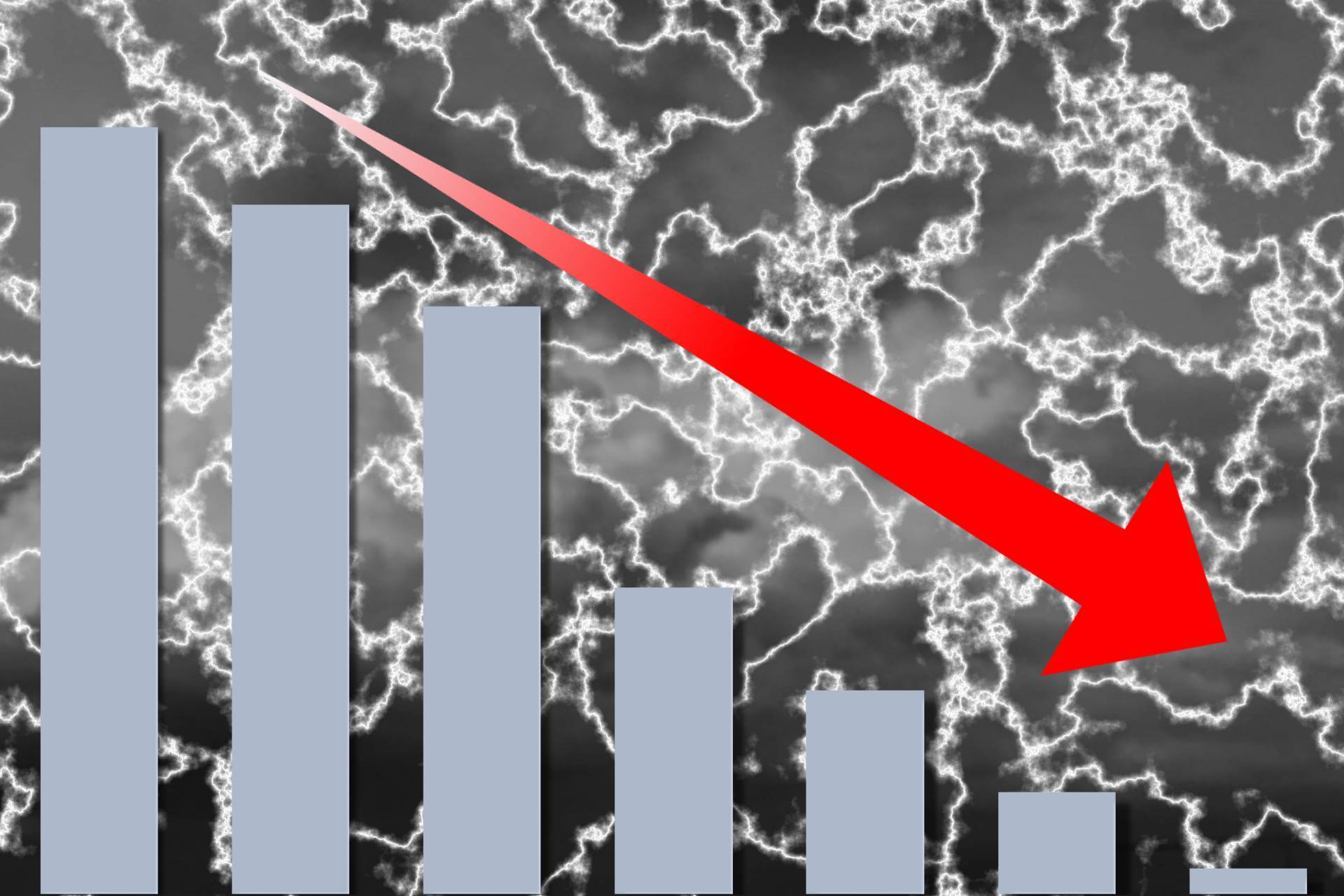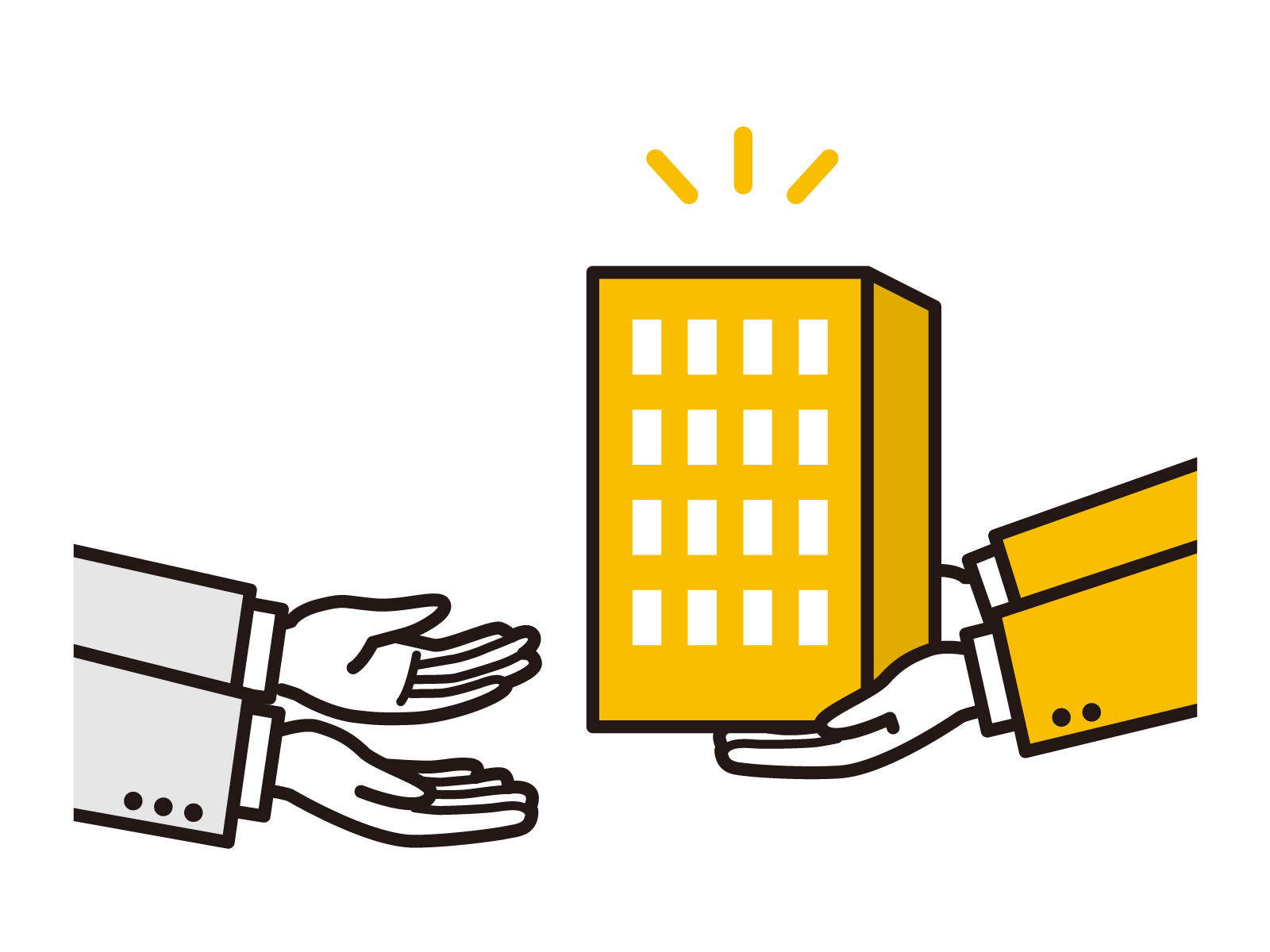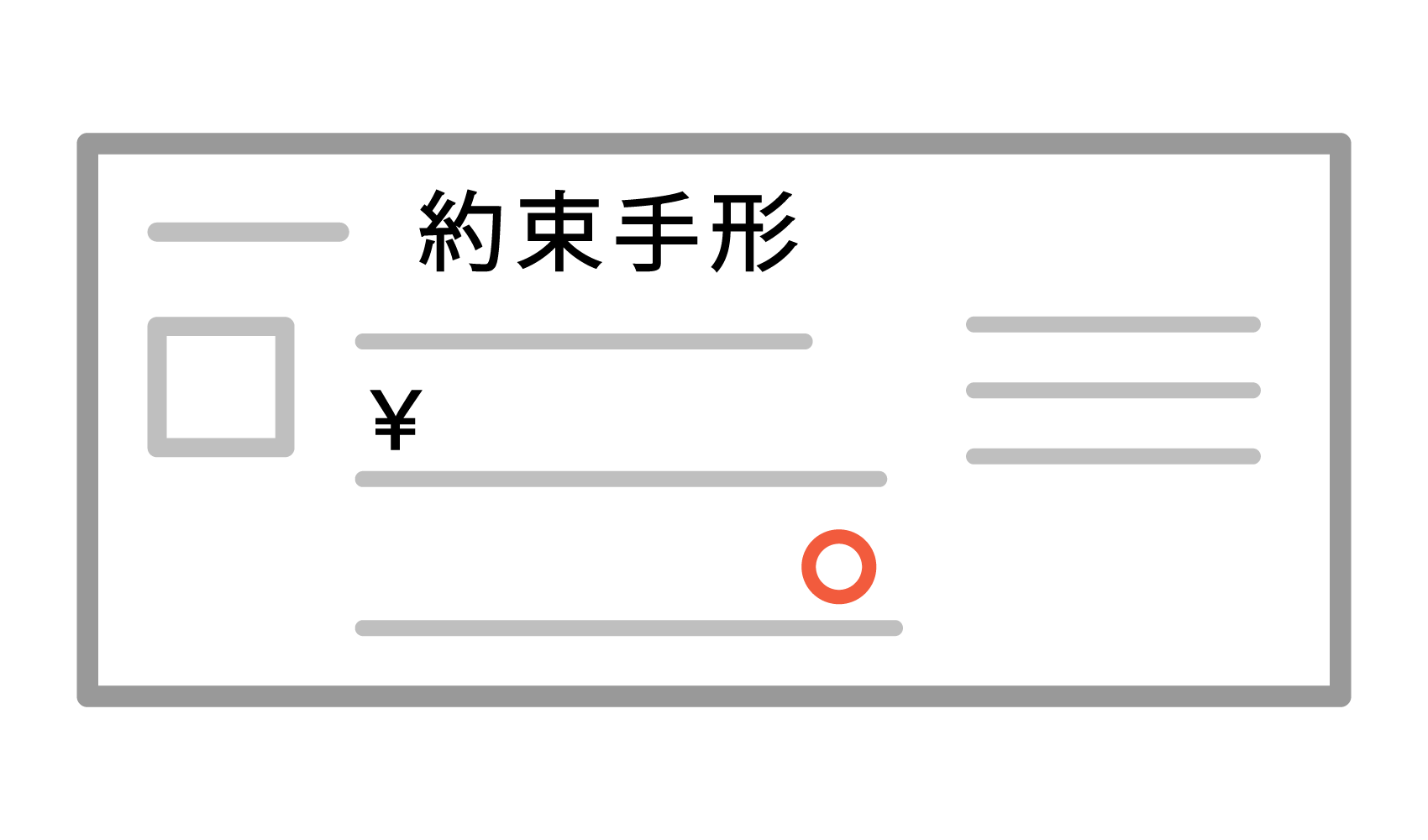
手形の期間短縮(60日以内に)
令和6年4月30日、公正取引委員会は、業界の商慣行、近年の金融情勢等を総合的に勘案し、指導基準等を変更することとし、令和6年11月1日以降、親事業者が下請代金の支払手段として、サイト(手形期間又は決済期間をいいます。以下同じです。)が60日を超える長期の手形等を交付した場合、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます。)の割引困難な手形の交付等に該当するおそれがあるとして、その親事業者に対し、指導する方針を公表しました。
<公表の要旨>
これまで、手形の支払期間に関する指導基準は、業種によって異なり、繊維業では90日、それ以外の業種では120日とされてきました。しかし、今回の改定により、すべての業種において手形の支払期間は60日以内に統一されました。これは業界の商慣行や金融情勢を総合的に勘案した結果です。令和6年11月1日から施行され、それ以降、親事業者が60日を超える手形を交付した場合には「割引困難な手形」と見なされ、指導対象となります。
また、経過措置として、施行日以前に交付された手形については、従来の基準(繊維業は90日、その他は120日)が適用されます。
さらに、今回の改定は一括決済方式や電子記録債権が下請代金の支払手段として使用される場合にも影響を及ぼします。これらの支払手段についても同様に支払期間が60日以内に短縮されることが定められており、親事業者は下請事業者に対して不利益な変更を行わないように注意する必要があります。
この改定は、下請事業者の資金繰りを円滑にし、健全な取引関係を維持することを目的としています。
手形のメリット・デメリット
「手形」は、将来の一定期日にお金の支払いを約束する証券で、企業間の取引でよく利用されます。手形には「受取手形」と「支払手形」があります。以下、それぞれについて内容の説明とメリット、デメリットを整理します。
受取手形
内容
受取手形は、取引先(顧客)から受け取る手形です。将来の期日に顧客が支払うことを約束した金額を表しており、手形を受け取った企業は、期日が来るまでに手形を銀行で割引して現金化するか、期日まで保有して支払を受けることができます。
メリット
・信用補完機能:手形は支払の約束を保証する書面なので、取引先の信用を補完します。
・資金調達の柔軟性:手形を銀行に持ち込んで割引すれば、期日前に現金化できるため、資金繰りの柔軟性が増します。
・取引の信頼性:手形は法的拘束力があるため、取引先が期日に支払う確度が高いです。
デメリット(リスク)
・不渡りリスク:取引先が期日に手形の支払いができない場合、手形が「不渡り」となり、現金を受け取れないリスクがあります。特に、二度の不渡りで取引先は「倒産」とみなされる場合もあります。
・資金繰りの悪化リスク:期日まで手形を現金化できない場合、短期的な資金不足に陥る可能性があります。
・割引料の発生:手形を期日前に現金化するためには銀行に割引料を支払う必要があるため、資金コストがかかります。
支払手形
内容
支払手形は、企業が仕入先などに対して支払うことを約束する手形です。手形を発行することで、期日までの支払いを延期することができます。手形の期日が来ると、その額を銀行から引き落として支払いを行います。
メリット
・支払い延期効果:支払手形を使うことで、実際の支払いを期日まで延期できるため、一時的にキャッシュフローを改善できます。
・資金繰りの調整:将来の支払いを予定して資金計画を立てやすくなります。
・取引関係の維持:手形を使うことで信用取引ができ、取引先との関係を円滑に保つことができます。
デメリット(リスク)
・支払い不能リスク:期日までに資金を用意できないと「不渡り」になり、信用問題に発展する恐れがあります。特に二度の不渡りで倒産するリスクがあります。
・信用の低下:支払手形を多用すると、企業の信用力が低下する可能性があります。これは、手形を多く使うことで「資金繰りが厳しいのではないか」とみなされる場合があるからです。
・利息の発生:期日に支払いをする際には、取引先が割引を行っていた場合、その割引にかかる利息分を最終的に負担することがあるため、コストが増える可能性があります。
手形は資金繰りの調整手段として非常に有効ですが、不渡りなどのリスクもあるため、十分な計画と信用管理が必要です。
手形の期間短縮や手形自体の廃止
支払手形を発行している企業が、その手形の期間を短縮したり、手形自体を廃止する場合の理由や方法、メリットとデメリットを整理します。
1 手形期間の短縮
支払手形の期間を短縮するとは、手形の支払期日を早めることを指します。これは、取引先と合意の上で行われることが多く、企業が取引の信頼性向上や取引先の要求に応じて実施する場合があります。
理由
・取引先からの要請:取引先が早期の支払いを希望している場合、手形期間を短縮することで、取引先との信頼関係を維持できます。
・企業の信用向上:支払手形の期間を短縮することで、「早く支払う企業」として取引先や銀行からの信用が高まる可能性があります。
・手形取引の縮小準備:手形取引を廃止する準備段階として、徐々に期間を短くし、最終的に手形を廃止することを視野に入れている場合があります。
メリット
・信用向上:早期に支払いを行うことで取引先の信頼を得やすくなり、長期的なビジネス関係の強化につながる可能性があります。
・取引関係の円滑化:取引先が資金繰りを気にせず、スムーズな取引が継続できるため、相手企業との取引が安定化します。
デメリット
・資金繰りへの負担:期日を早めることで、自社の資金繰りが厳しくなる可能性があります。手元資金の確保が難しくなるリスクがあります。
・運転資金の圧迫:手形期間の短縮は、企業が即時に支払いを行うため、運転資金に余裕がなくなるリスクが伴います。
2 手形取引の廃止
支払手形そのものを廃止する企業も増えています。手形の代わりに、銀行振込や電子決済などの即時決済手段を採用するケースが多いです。
理由
・手形の管理コスト削減:手形を発行するには、手形の印刷、管理、割引にかかるコストが発生します。これを廃止することで、事務的な負担が軽減されます。
・信用リスクの軽減:不渡りが発生した場合の信用リスクを回避できます。また、相手方の信用を確認する必要もなくなり、手続きがシンプルになります。
・資金決済の迅速化:銀行振込や電子決済などの即時決済手段に切り替えることで、資金の流れがスムーズになり、取引が迅速に進むようになります。
メリット
・管理コストの削減:手形を発行しないことで、印刷や管理、手数料などのコストを削減できます。
・不渡りリスクの回避:手形取引を廃止することで、不渡りリスクがなくなり、企業の信用リスクを軽減できます。
・キャッシュフローの改善:電子決済や振込を利用することで、資金の流動性が高まり、キャッシュフローの安定に寄与します。
デメリット
・即時支払いの資金負担:手形を廃止することで、すぐに現金を用意しなければならず、資金繰りが厳しくなる可能性があります。
・取引先との交渉が必要:手形取引を廃止する際、取引先に対して新しい決済方法を導入する必要があり、取引先との調整が必要です。特に手形文化に依存している企業の場合、抵抗があることも考えられます。
手形取引を続けるか、廃止するか、またその期間を調整するかは、それぞれの企業の資金状況や取引関係に依存します。資金繰りの見通しや取引先の期待に応じて、適切な判断が求められます。