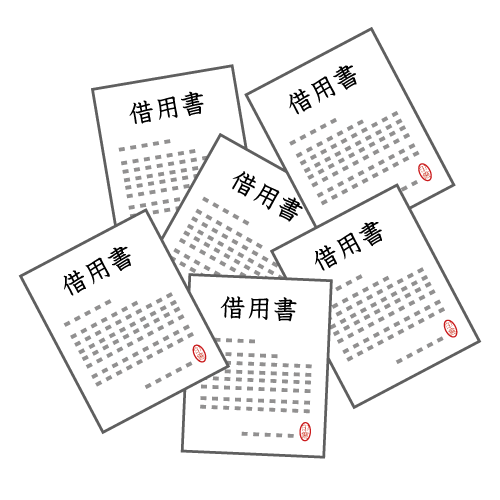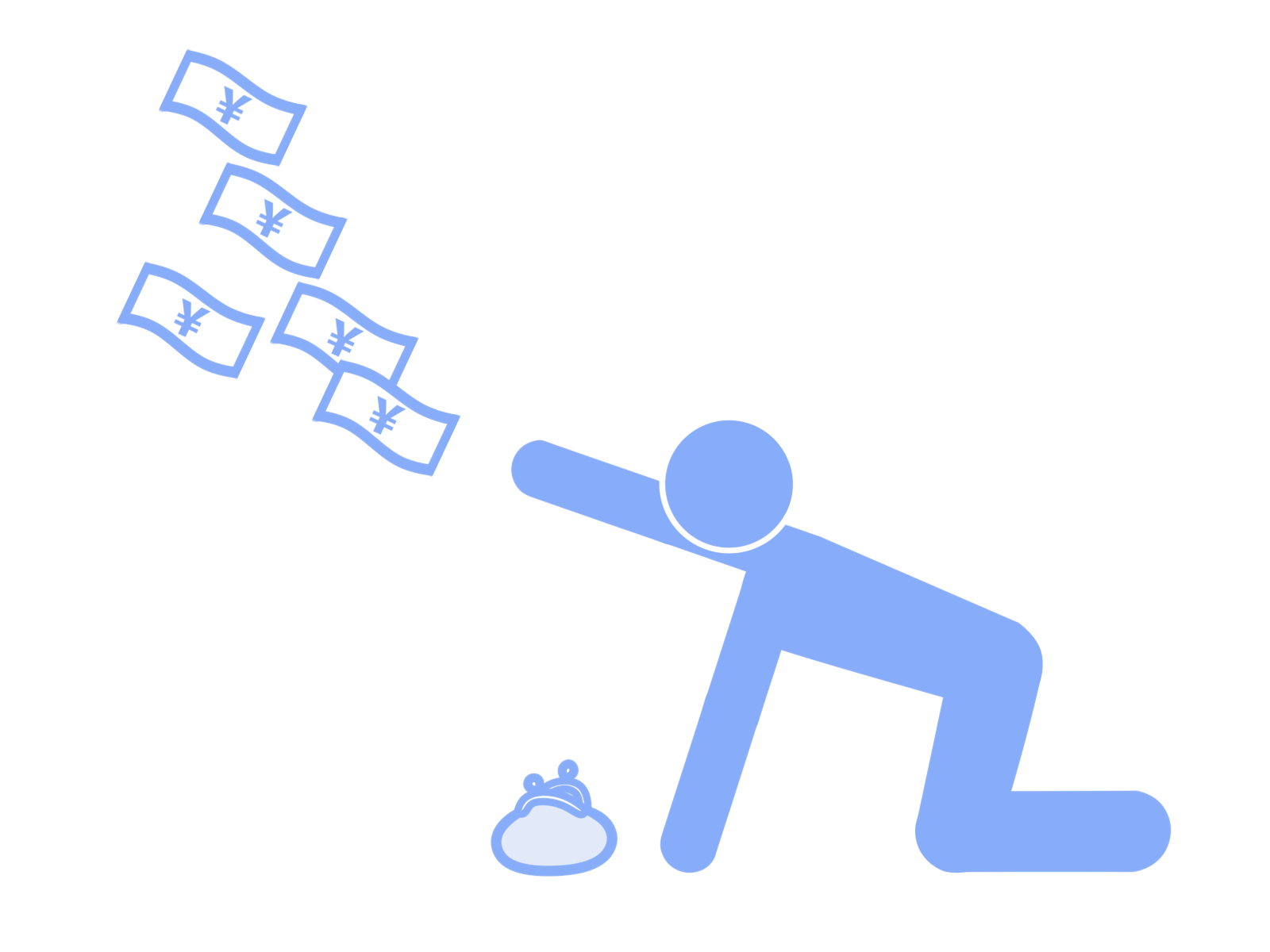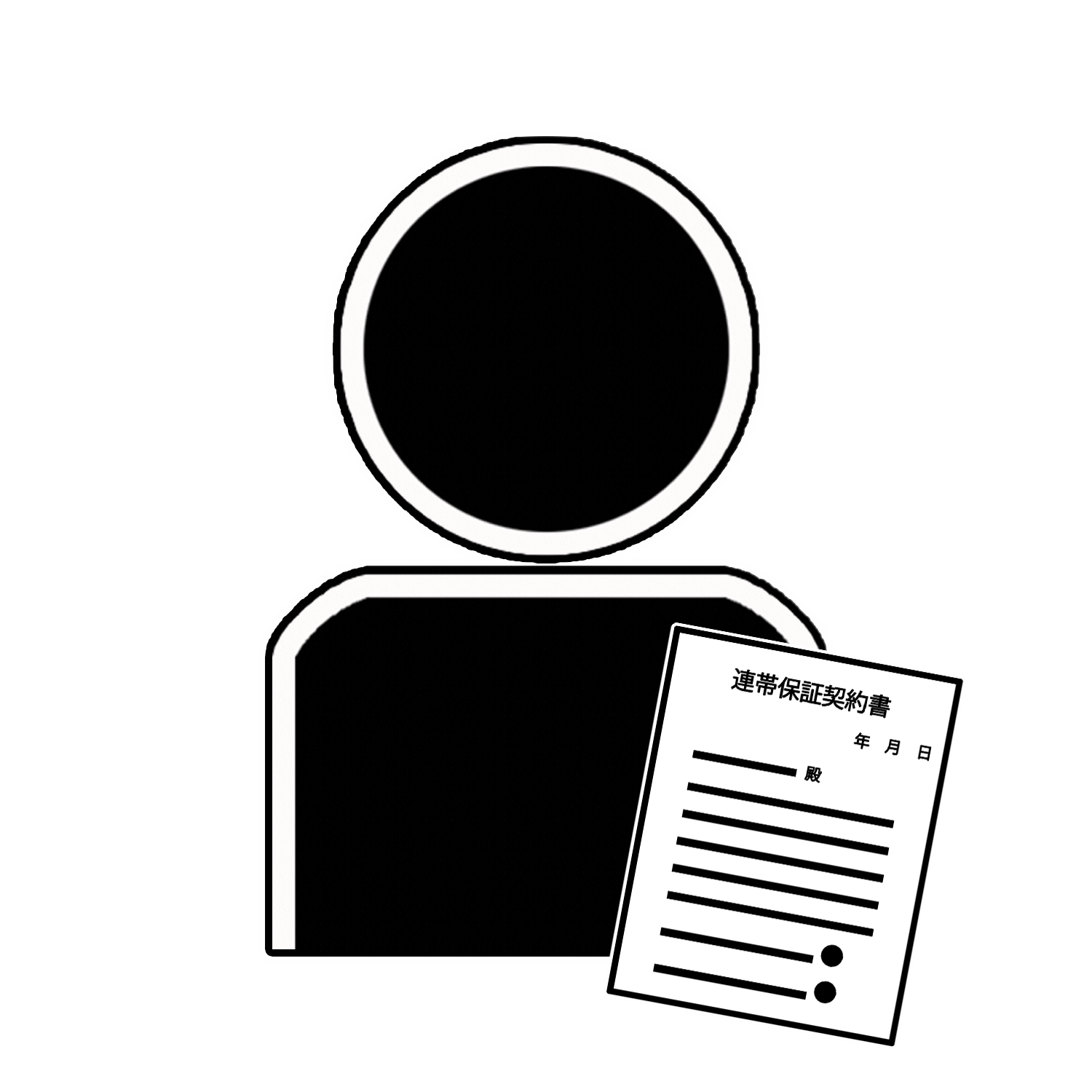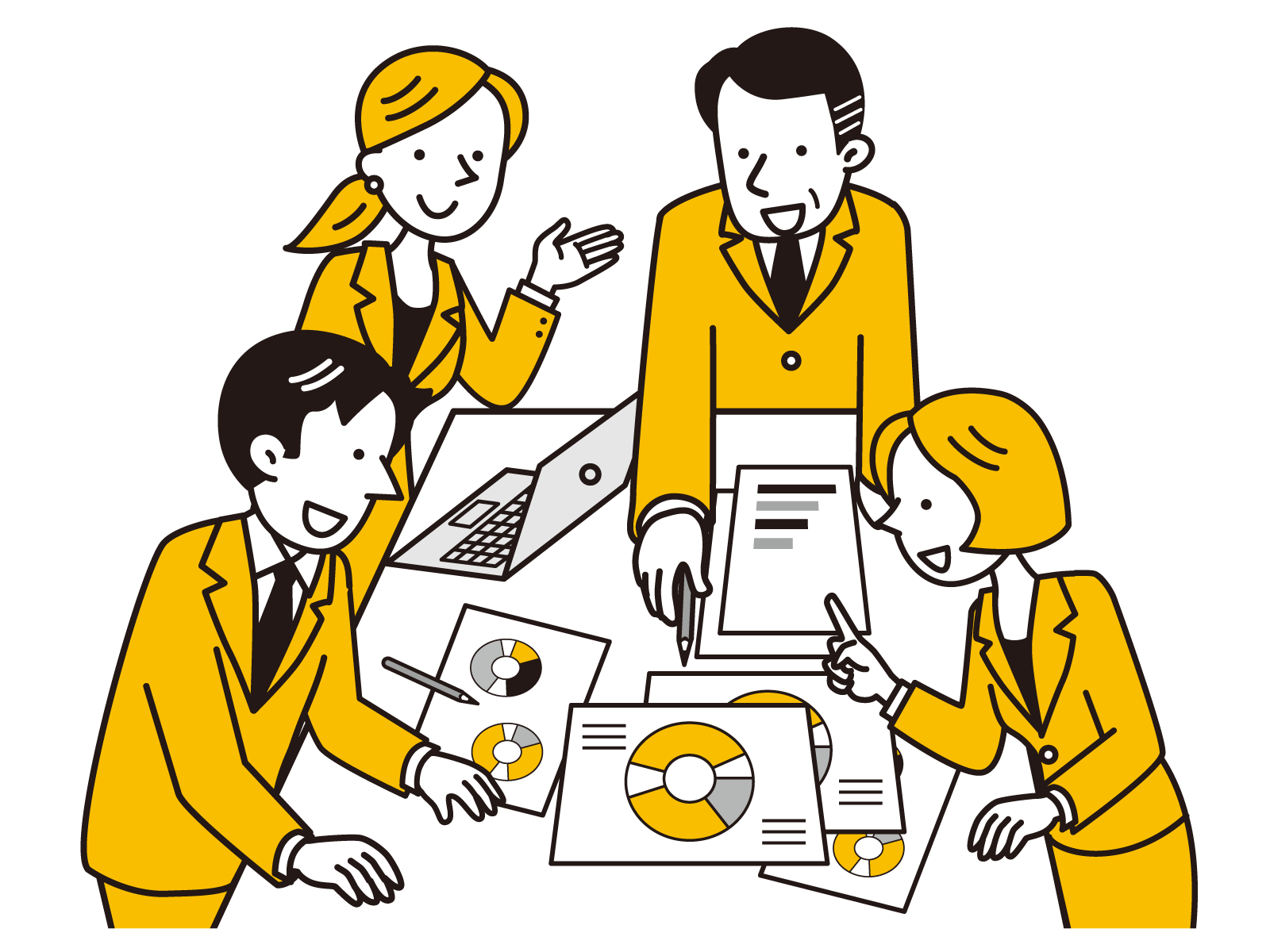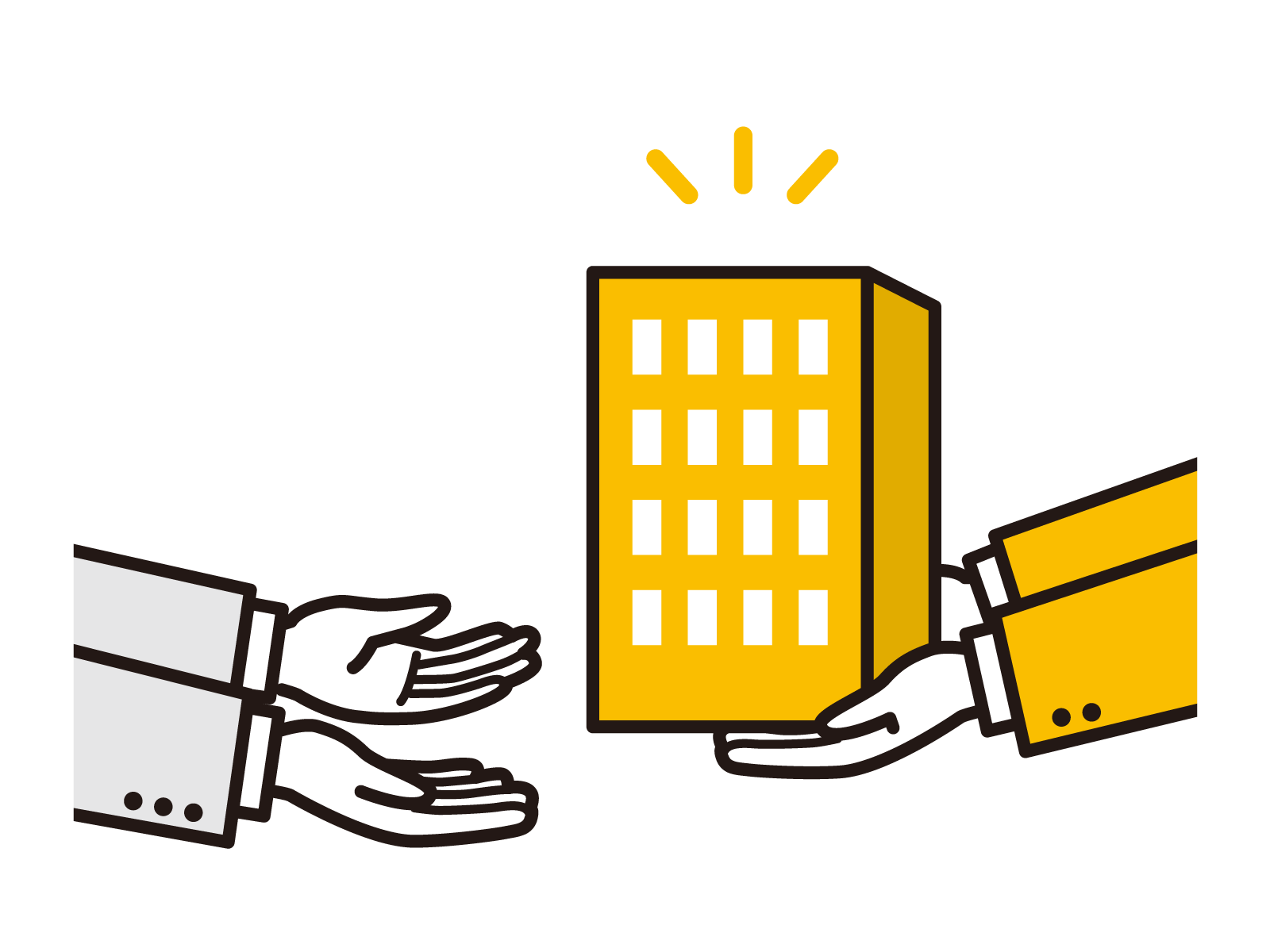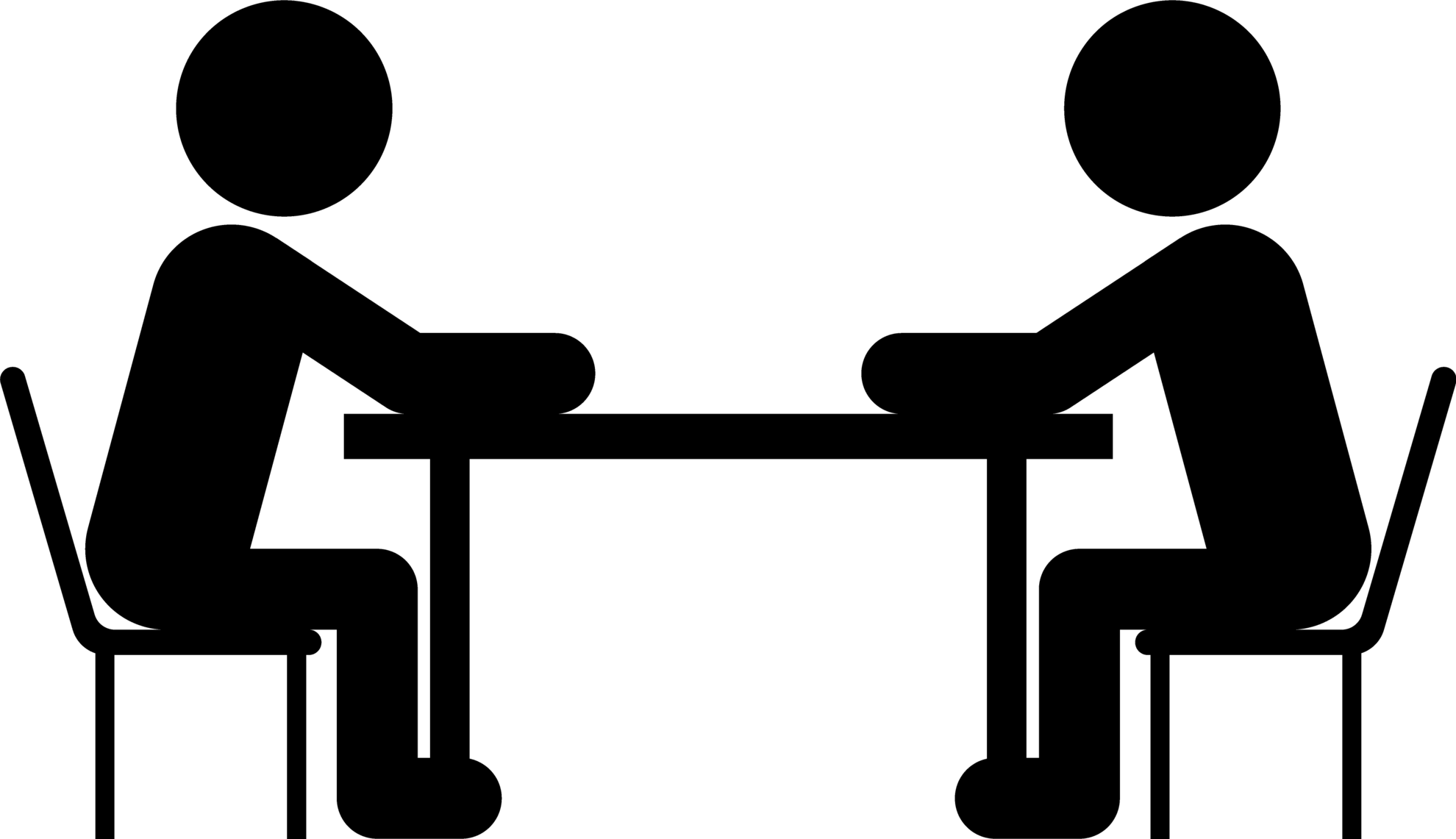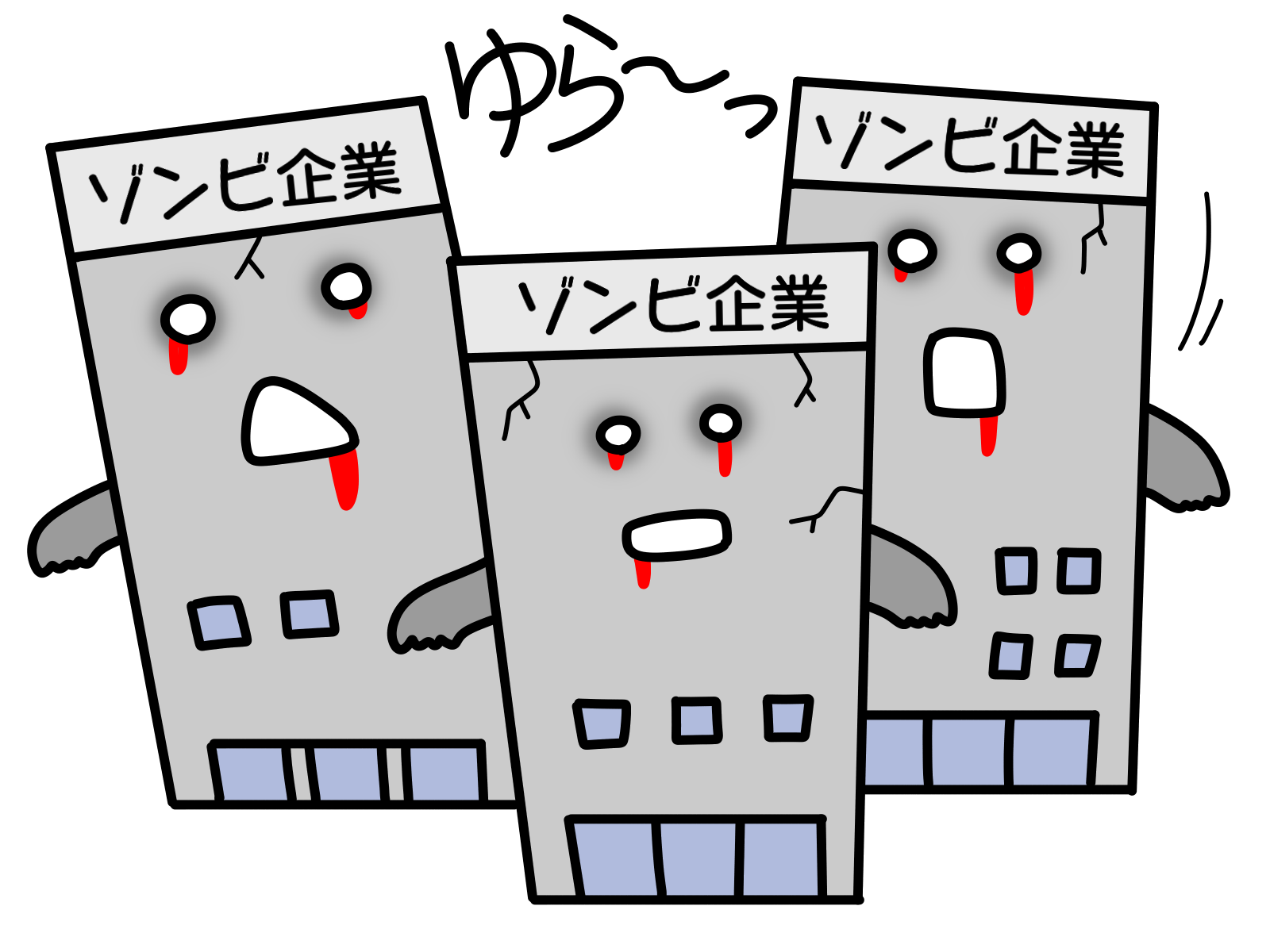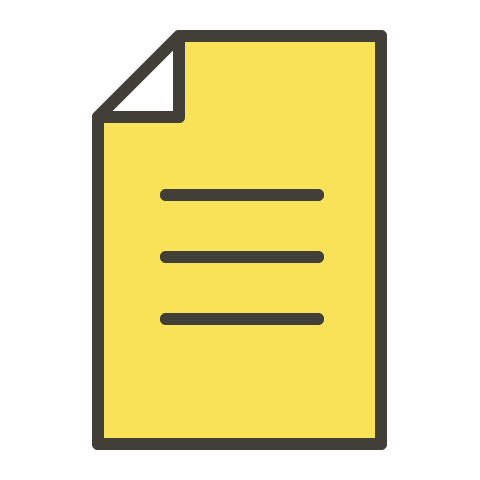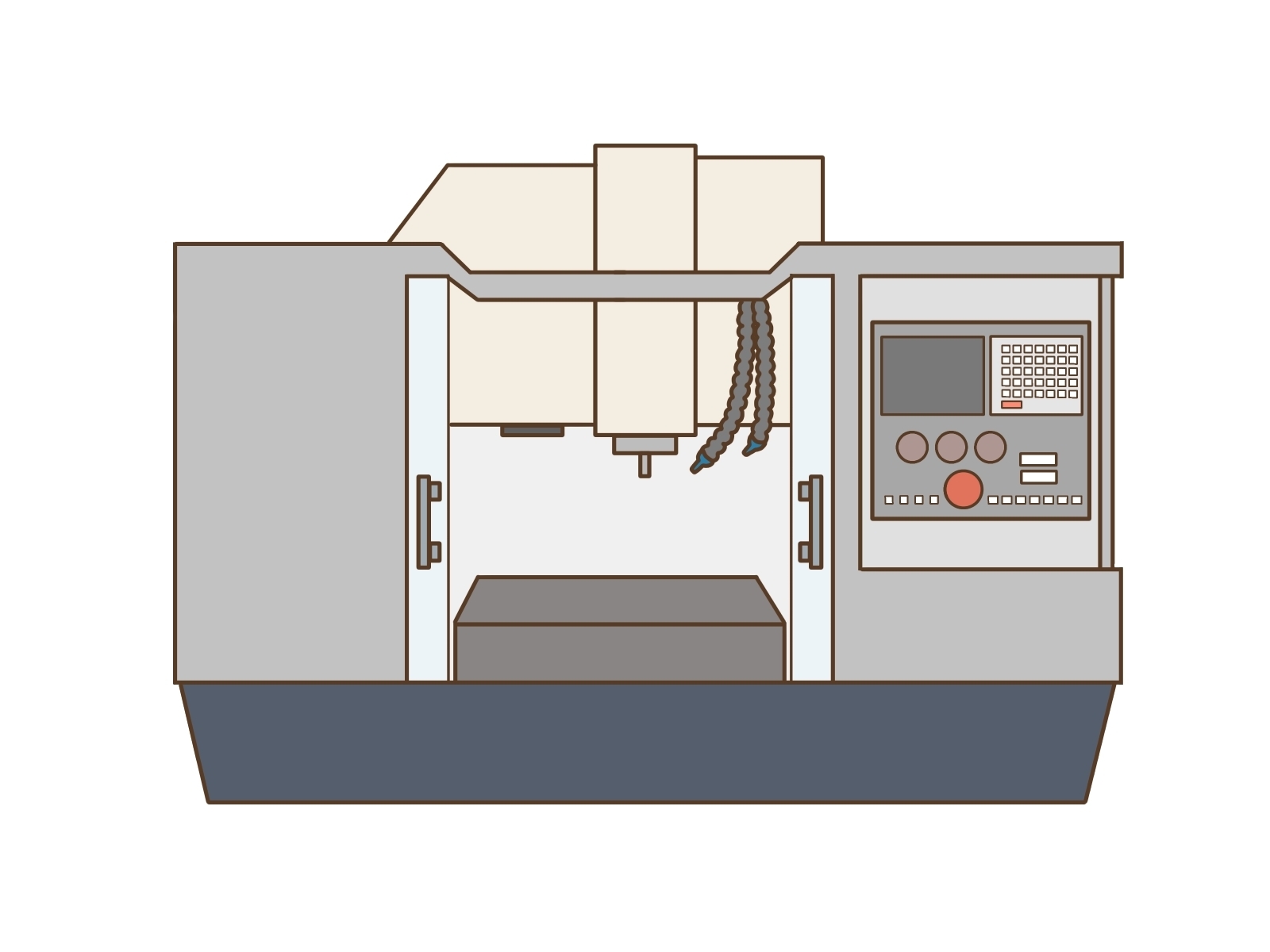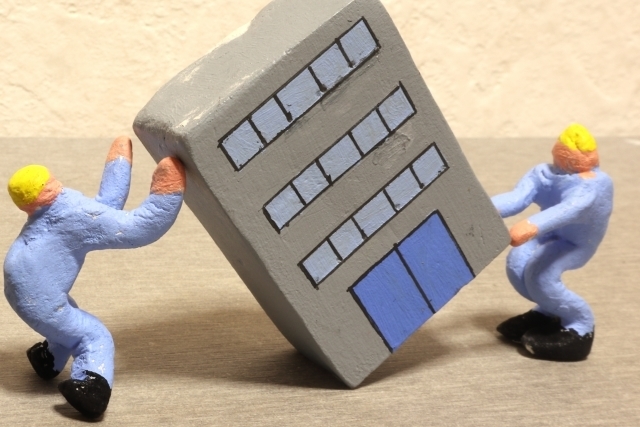
こんにちは。株式会社事業パートナーの松本光輝です。
企業経営において、借入金の返済負担や業績悪化によって立ち行かなくなるケースは少なくありません。しかし、だからといってすぐに廃業や破産を選択するのではなく、「第二会社方式」という選択肢も検討に値します。この方式は、旧会社の負債や問題点を整理しつつ、新会社での事業再生を図るもので、一定の条件を満たすことで有効に機能します。
今回は、この「第二会社方式」を実行するにあたって、最低限満たしておくべき3つの絶対条件について解説いたします。
(1) 利益が見込めること
第二会社方式は、将来性のある事業を守るためのスキームです。そのため、赤字が続き、立て直しの見通しが立たない事業をそのまま引き継いでも意味がありません。
ポイントとなるのは、旧会社で赤字体質だったとしても、事業構造の見直しやコスト削減などを通じて、収益の改善が可能であるという合理的な経営計画があることです。
例えば、人件費や家賃の見直し、非採算部門の整理、営業戦略の転換などを行い、第二会社で黒字化できる見込みがあれば、そのスキームは現実味を帯びてきます。逆に、今後も赤字が続くと判断される事業では、第二会社方式は機能しません。
(2) 取引先との継続的な取引が可能であること
第二会社方式では、旧会社と新会社は別法人となります。従って、既存の取引先とは、あらためて新会社として契約を締結する必要があります。
多くの取引先は過去の取引実績や信用をベースに継続取引を検討してくれますが、特に大手企業や上場企業との取引では、新たな信用審査や稟議が必要になるケースもあります。そのため、事前に取引先との関係性を確認し、新会社での継続的な取引が可能であるかを見極める必要があります。
取引先から「会社が変わるなら今後の取引は難しい」と判断される場合は、第二会社方式による再出発は困難になります。
(3) 借入金返済がなければ経営の継続が可能であること
倒産の主な原因の一つが、「借入金の返済負担」です。元本の返済だけでなく、利息の支払いも資金繰りを逼迫させる大きな要因となっています。
第二会社方式では、旧会社に残る借入金を整理し、新会社には引き継がないのが基本です。したがって、新会社には金融債務がない、あるいは著しく軽減されている状態でスタートすることになります。
この際重要なのは、「借入金の返済負担がなければ、新会社では資金繰りに余裕があり、黒字経営が可能である」ことが、数字で証明できることです。収支計画書や資金繰り表を用いて、将来的に安定した経営ができるという根拠を提示することが必要です。
資金繰りに行き詰まり、借入金の返済に苦しむ企業にとって、「第二会社方式」は新たな一歩を踏み出すための有力な選択肢となり得ます。ただし、実行にあたっては、(1)利益が見込めること、(2)取引先の継続が可能なこと、(3)借入金の返済がなければ経営が成り立つこと、という3つの絶対条件を満たす必要があります。
当社では、これらの条件を満たす可能性がある企業様に対して、第二会社方式による再生支援を行っております。借入金の返済等でお悩みの経営者の皆様、ぜひ一度ご相談ください。