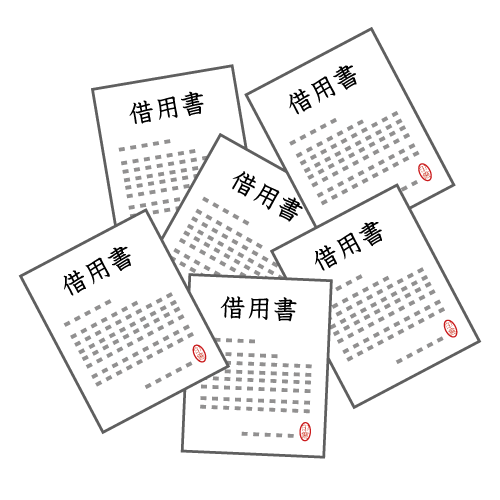中小企業の経営者が事業継続に行き詰まったとき、最初に相談する相手は誰か。
多くの場合、それは長年付き合いのある「顧問税理士」です。資金繰り、決算、融資、節税――日常的に経営の内情を共有し、最も信頼を寄せている存在こそが税理士の先生方であり、経営の「最後の判断」にも影響を与えるキーパーソンです。
今回のテーマは「廃業支援」
顧問先の経営者にとって、“終わり”を考えるのは容易なことではありません。しかし、事業が再生もM&Aも難しい段階に来ているならば、現実的かつ前向きな「撤退戦略」として、税理士の先生が声をかけてあげることが、経営者を救う大きな支えとなります。
廃業支援における税理士の重要な役割
「廃業支援」は、税理士の先生がもっとも力を発揮できる分野の一つです。
というのも、廃業には次のような専門的な対応が必要であり、それぞれに税務的な影響があるからです。
・資産・負債の整理と処分
・最終申告・清算決算
・残余財産の分配と税務対応
・未払い債務や引当金の処理
・個人保証や私財への影響整理
これらは、法律や会計の知識だけでは対応しきれません。税理士の先生が、経営者の人生設計や資産状況まで視野に入れてアドバイスできる存在だからこそ、「安心して話せる」場が生まれるのです。
「廃業支援チーム」による伴走が必要な理由
とはいえ、廃業には税務以外にも多岐にわたる課題が生じます。
・金融機関との交渉やリスケ対応
・従業員の退職・転職支援
・売掛金や在庫・設備の回収・売却
・家族の生活基盤(自宅や保有資産)の保全
・借入の連帯保証や法的リスクの整理
こうした局面では、税理士の先生お一人で対応できる範囲を超えてしまうことも多いのが現実です。そこで重要になるのが、他士業や専門家との連携による「廃業支援チーム」の構築です。
当社では、事業再生・廃業支援に精通したコンサルタントを中心に、金融機関との調整や資産保全スキームの立案、必要に応じて弁護士・社労士・不動産の専門家と連携しながら、経営者の「ソフトランディング」を支援しています。
当社が税理士の先生と連携することで提供できる価値
当社では、これまで多くの中小企業の再生や撤退に関わってきた経験を活かし、次のような形で税理士の先生方と力を合わせることができます。
・経営者との初期面談に同席し、判断の材料を整理
・再生/M&A/廃業の選択肢を検討・提案
・債権者(金融機関等)との交渉支援
・経営者の自宅や資産を守るためのスキームの提案
・必要に応じた弁護士・他士業との橋渡し
「廃業ありき」ではなく、まずはすべての可能性を検討し、それでも難しい場合に「廃業という合理的な道筋」を示すことを大切にしています。
その際、税理士の先生の存在は欠かせません。数字の裏付け、経営者の信頼、そして廃業後の税務処理を通じて、最後まで経営者に寄り添う力をお持ちだからです。
「先生からのひと言」が経営者を救うこともある
廃業という選択は、経営者にとって感情的にも非常に重いものです。
「もう限界かもしれないけれど、誰にも言えない」――
そうした思いを抱えたまま、時間だけが過ぎてしまうことも多くあります。
そんなときに、信頼する税理士の先生から
「無理に続けるより、次の人生に進む道もありますよ」
という言葉があれば、経営者は救われるかもしれません。
顧問先に「悩んでいる経営者」がいれば、ご紹介ください
当社では、廃業を「失敗」や「終わり」としてではなく、経営者の新たなスタートを支える出口戦略としてとらえています。
「このまま続けるよりも、きちんと幕を下ろした方がいいのでは」
「再生やM&Aも難しく、八方ふさがりに見える」
――そんな顧問先がいらっしゃれば、ぜひ一度ご紹介ください。
税理士の先生と力を合わせて、経営者が最善の判断を下せるよう、全力でサポートいたします。
次の世代につなげる「承継」も、経営を終える「廃業」も、どちらも価値ある経営判断です。
今後も、税理士の先生方と共に、中小企業の経営者にとって「最後まで信頼できる支援者」でありたいと願っています。
顧問先の「最後の出口戦略」、私たちと一緒に支援しませんか?
事業再生を専門とする当社では、「再生」「承継」「売却」の可能性を探ったうえで、やむを得ず「廃業」という選択に至る中小企業の支援にも力を入れております。
特に税理士の先生方が顧問先の最も信頼できる相談相手であることを、私たちも日々実感しています。
当社の廃業支援の強みは、以下のとおりです:
・借入金返済への現実的な対応力
事業再生の現場で培ったノウハウを活かし、金融機関との調整やリスケ交渉にも精通しています。
・経営者の生活基盤を守る支援
自宅や保有財産を極力守る視点から、「引き際」の設計を行います。
・「廃業ありき」ではない柔軟な対応
状況に応じて、事業再生やM&Aによる売却の選択肢も併せてご提案可能です。
・弁護士をはじめ、多様な専門家との連携体制
法的整理が必要な場合も、速やかに対応できる体制を整えております。
経営者が最終判断を下すまでには、多くの迷いと不安があります。
「無理に続けて消耗するより、今が引き際かもしれない…」
そんな顧問先がいらっしゃいましたら、ぜひ私たちをご紹介ください。
税理士の先生方と連携し、経営者にとって後悔のない選択ができるよう、丁寧に寄り添った対応をお約束いたします。